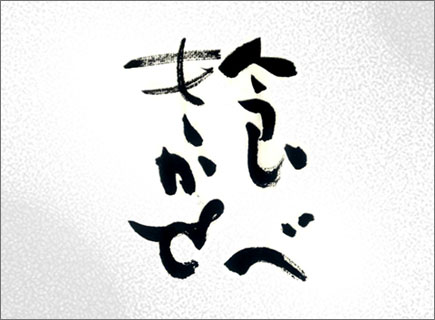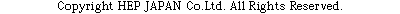|
| お祝い事には欠かせないお赤飯。 |
 |
| 古来より、日本では赤色が珍重されてきました。 |
 |
| 日本人にとって、赤は穢れを払う清浄なる色。魔よけの意味もありますよ。
|
 |
| |
 |
| さて、その美しい赤色の素になるお赤飯の豆ですが、 |
 |
| 関西では『小豆』、関東では『ささげ』を使います。 |
 |
| 両方ともマメ科ササゲ属のもので、そっくりな姿形をしています。 |
 |
| ささげの方が小豆より少し大きいですが、とても良く似ていますよ。 |
 |
| 味はというと、一般には小豆の方が優れていると言われています。 |
 |
| |
 |
| では、関東ではどうして美味しいほうの小豆を使わないんでしょうか?。 |
 |
| その答えはそれぞれの土地の歴史にあります。 |
 |
| 関東は言わずと知れた江戸文化。つまり、武士の文化なのです。 |
 |
| 実は小豆は味は良いのですが、加熱すると『胴切れ』といって |
 |
| 皮が破裂してしまうことが多いのです。 |
 |
| その胴切れが切腹を連想させ、武家社会では「縁起が悪い!!」となったわけですね。 |
 |
| |
 |
| その点、ささげは味は落ちるものの、胴切れを起こすことはあまりありません。 |
 |
| 武士の文化が根強い関東でささげが用いられるようになったのも納得できます。 |
 |
| では一方の関西はというと、昔から商人の町、食い倒れの町です。 |
 |
| 胴切れなんてなんのその、「美味しければええやん!」の精神です。 |
 |
| 美味しさ一番、安さ一番、見た目はその次ですから・・・。 |
 |
| かく言う私も生粋の関西人ですから、お赤飯には小豆を使いますよ。 |
 |
| |
 |
| 今は炊飯器で作る人、市販のものを買う人も増えていますが、 |
 |
| キチンと作ったお赤飯は格別なものです。 |
 |
| 振り返ってみれば、人生の節目毎に母が作ってくれたお赤飯は、 |
 |
| お祝いの言葉以上に、母の想いが詰まっていた気がします。 |
 |
| これからは私もお祝いの気持ちを込めて、美味しいお赤飯を作っていきたいと思います。 |
 |
| |
 |
| |
 |